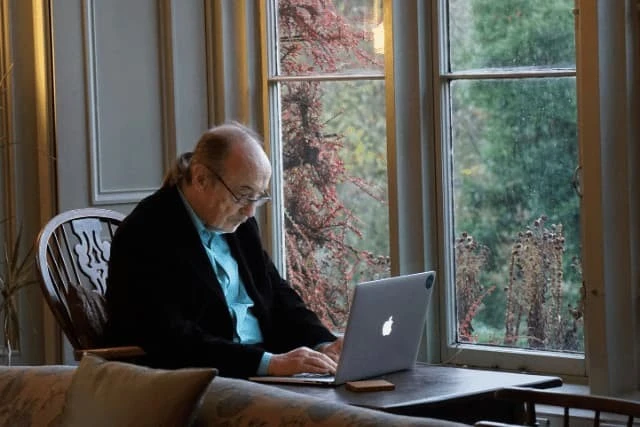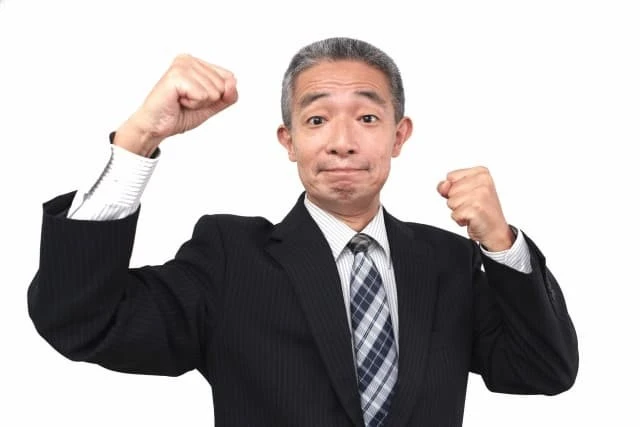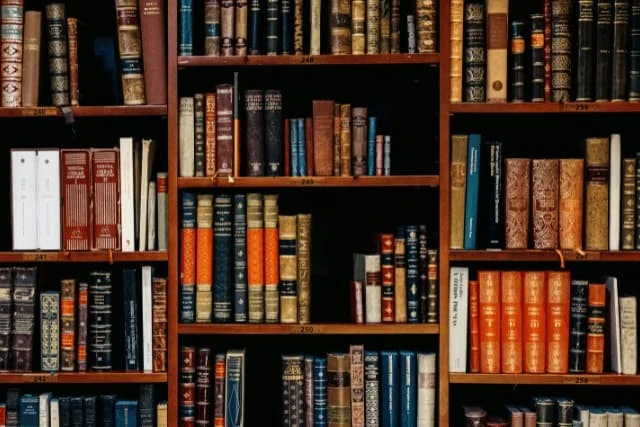「シニアでも働き続けたい」と答えた人は80%!職種や年収、苦労する点などを60歳以上で働く100人に大調査!
少子高齢化が進み、労働人口の減少が懸念されている現代の日本。それを背景として、2025年4月から「65歳までの雇用確保」が義務化され、企業は「65歳までの定年の引き上げ」「希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入」「定年制の廃止」のいずれかへの対応が義務付けられました。医療の発展により健康寿命も伸び、定年後も仕事への意欲をもつシニア世代の人々にとって、定年後も長く働くキャリアの選択肢は今後もより広まっていくでしょう。
では実際に、すでに定年退職後もシニアとして働いている人々は、どのような理由や目的から働いているのでしょうか。
今回の記事では、シニアとして働いている100人にアンケートを実施し、職種や年収、シニアとして働き続ける理由について調査を行いました。シニアとしての強みはもちろん、不安に感じている点や、それを解決するための工夫などについても聞いているので、シニアとして働くことに興味がある人はぜひ参考にしてみてください。
シニアで働く人たちの気になる職業は?
シニアで働く人達は、それまで培ってきたスキルや知識、社会経験など、現役世代とはまた違った大きな強みを持っています。定年退職後も、その強みを活かして第二のキャリアを歩むというのはひとつの選択肢と言えるでしょう。実際に今回の調査でも、現在の仕事を過去に本業やアルバイトで経験したと回答した人は合わせて71%と大多数を占めました。
また、職種は「専門的・技術的職業(医師、弁護士、教師、研究者、エンジニアなど)」(19%)、「サービスの職業(介護職員、美容師、調理人、家政婦など)」(18%)、「事務的職業(一般事務、会計事務、営業事務)(15%)など、幅広い職業の回答が集まりました。また、「その他」(10%)と答えた中にはこのような職業をしている人も。
・ウェブ記事のライティングやブログ運営
・データの集計分析や入力
・公益社団法人の事務
・自動車整備
・障がい者の就労支援施設で作業の指導や就労サポート
・倉庫でのピッキング作業
・保育園での保育補助
IT業務など在宅やオフィスでできるデスクワークもあれば、出勤や体力仕事が必要な業務なども多くあり、もちろん個人の経験やスキルにはよりますが、シニア人材だとしても就ける職種の幅は広く、自分に合った職業や仕事内容などを選ぶ余地が十分にあることがわかります。
シニアになっても働こうと考えた理由は?
定年を過ぎた後もシニアとして働く理由は様々です。働くこと自体が生きがいとなっていて年齢を気にせず仕事をし続けたいと考えたり、第二の人生で好きな仕事や気になる仕事にチャレンジしたいといったポジティブな理由もあれば、年金だけでは家計が成り行かなかったり、貯蓄が心許なかったりと金銭的な不安を理由とする場合もあります。
実際に今回の調査で最も多かったのは、「働かないと家計が厳しかったから(年金だけで生活をしていくのは難しいと感じているから)」(48%)でした。一方で「いくつになっても働きたかったから」や「やってみたい仕事があったから」など前向きな理由も37%と決して少なくない人数からの回答となっています。
年収は「200〜299万円」(26%)、「300〜399万円」(25%)とほぼ同程度で並び、次点で「100〜199万円」(20%)「〜99万円」(15%)と続きました。シニアでも働ける職種の幅は広い分、時給や月収は契約形態や専門的なスキルの有無、勤務できる時間などでも大きく変動します。もし今シニアで働くことを検討している方は、自分の働く目的に合った収入を確保できるかどうかという点で職種を探してみるのも一つの選択肢かもしれません。
収入の使用先(複数回答可)は「家計」(81%)が大多数を占めましたが、一方で「娯楽(趣味や旅行など)」(42%)や「交際費」(14%)など余暇を楽しむ目的での活用も多く回答が集まったことは印象的です。シニアになっても働くことの良さとして、仕事のやりがいや生き生きとした生活の実現だけではなく、老後の金銭面に余裕が出ることでより余暇を充実させることができるようになることも挙げられるかもしれませんね。
シニアとして働く上での「体力への不安」という課題
「いくつになっても働きたい!」と思う一方で、シニアとして働く上では体力や体調面などのリスクや不安はつきもの。仕事が負担となって身体を壊してしまっては本末転倒です。実際、今回の調査でも「働く上で大変だと感じていること」としてやはり最も多く挙げられたのが「体力」(74%)でした。
一方で、以下のような声もありました。
「老後の生活不安のために働き始めましたが、必ずしも働かなくてもいい状況で誰にも強制されずに自発的に働いていると、精神的に負担には感じず、むしろ生き生きとしてくるようになりました。自分自身で頭を使って身体を動かすことは、むしろ健康にいいと感じています」
「働くことをやめると生活習慣が不規則になり、体力が衰えていくだけだろうと感じているので、働くことは体力作りの一環だと考えています」
「週3〜4日勤務で、正社員時代と比べて割と自由な時間もあり、日々の充実感が得られています。人とコミュニケーションをとることで、認知機能低下の予防にもつながっていると感じています」
仕事を続ける上で「どれだけ体力が持つか」という不安を感じる人は多い一方で、仕事を続けること自体が体力作りや脳の健康にもつながっているとも言えます。また、健康不安に関しては、このような工夫をしているという回答も集まりました。
「私は中性脂肪が高めになりがちなので、定期的にかかりつけ医で血液検査を受け、値が悪くなったら自発的に食事療法をするようにしています」
「早寝早起きなど規則正しい生活を心がけ、筋トレや身体にいい食事をするようにしています」
「疲れやすいので休日以外でも疲れを感じたときは有給を使って身体を休めるようにしています」
若かった頃に比べると、どうしても疲れやすくなっていたり、体調を崩しやすくなってしまうということを念頭に、日々自身のケアを意識したり、疲労を感じたら無理をせずに休んだりすることも長期的に働き続けることを考えると大事なことかもしれませんね。
シニアだからこそ活かせる経験やスキル
上記のような体力面の不安などがある一方で、若手や中堅と比較して、知識や経験などを多く持っていることはシニア人材の強みと言えるでしょう。では、「シニアだからこそ仕事をする上で活きている」と感じられる瞬間はどのようなものがあるのでしょうか。今回の調査ではこのような声が集まりました。
「これまでのシステム開発経験を活かして、現場の作業をフォローすることができています」
「社会経験が長いため、イレギュラーな事態が発生しても、それほど慌てずに対処することができます」
「これまでの趣味や経験が商品選定に役立っています」
「それまでの仕事や経験で得た知識や技能を後輩や若手に引き継いでいます」
「配送ドライバー職で培った道路の知識や土地勘などが仕事に活かされています」
「目先の結果にとらわれず、長期的な目線で業務を遂行することができます」
思わぬトラブルや想定外の事態にも冷静に対応できたり、知識や人脈を若手に引き継いでいくことができるのは、どんな職種においてもシニア人材だからこそできる強みです。そういった強みを活かしながら誰かの役に立ったり、収入を得たりすることができるのは、人生の張り合いややりがいにもつながるでしょう。
実際に「仕事にやりがいを感じる」と答えた人は「とてもそう思う」「ややそう思う」合わせて75.51%、「今後も働き続けたい」と答えた人は「とてもそう思う」「ややそう思う」合わせて80%と大多数を占めました。
シニアでも働き続けることによって、金銭的な余裕が生まれたり、心身ともに生き生きと過ごせたり、第二の人生のキャリアを考えることは人によって様々なメリットがあるようです。本業の知識や経験を活かすのもいいですし、あえて新しい職種にチャレンジしてみるのもいいですね。もしシニアとしてのキャリアに興味がある方は、転職サイト「PR市場」のシニア専門求人でもシニア求人に特化して掲載していますので、よければ参考にしてみてください。