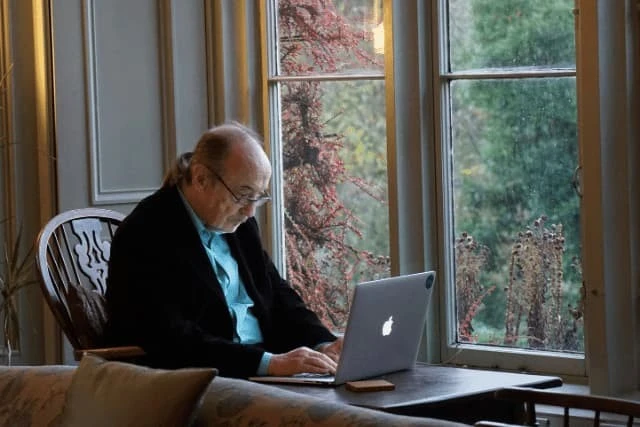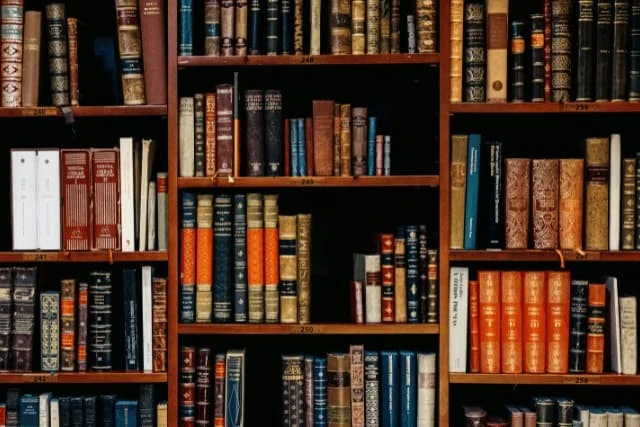登録販売者は何歳まで働ける?年齢制限の有無や資格の取り方を解説
公開:2025/03/30 更新:2025/03/30
ドラッグストアなどで、「登録販売者」を見かけたことがある方は多いのではないでしょうか。登録販売者の資格に関心があるけれど、何歳まで働けるのか不安に思っている方もいるかもしれません。
実は、登録販売者の資格取得に年齢制限はありません。シニア世代の方でも資格を取れるため、登録販売者はセカンドキャリアとして人気の職種ともいわれています。
そこで本記事では、登録販売者の資格の取り方や働ける場所、登録販売者として働く際に押さえておきたいポイントなどについて解説します。
登録販売者に年齢制限はある?
結論からいうと、登録販売者として働くことに年齢制限はありません。働くには資格が必要ですが、シニア世代でも資格を持っていれば何歳でも働けます。パートやアルバイトでの求人募集も多いため、登録販売者は定年後の仕事としても注目を集めています。
登録販売者になるメリット
登録販売者の資格を取れば、有資格者として重宝されるほか、シニア世代でもパートやアルバイトなどで長く働けるでしょう。医薬品を扱うので薬の知識も身につくため、自身や家族の健康管理にも役立つと考えられます。
登録販売者の仕事内容
登録販売者は、医薬品や健康食品販売などの業務を担当します。具体的には店舗を訪れたお客さんへ一般医薬品の説明や販売をしたり、相談を受けたりするのが主な仕事です。
ほかにも売り場づくりやレジ業務 、売上や在庫管理も登録販売者の仕事です。接客だけでなく、品出しなどの力仕事も求められるでしょう。
登録販売者の勤務先
では、登録販売者の勤務先はどのような場所があるのでしょうか。勤務先の一例を紹介します。
ドラッグストア
登録販売者の勤務先で代表的なのがドラッグストアです。一般医薬品だけでなく、医薬部外品や健康食品、サプリメントなどの幅広い商品を取り扱っているため、多方面の知識が必要となります。
お客さんの相談を受けて症状に合わせた薬を提案するなど、接客の要素も大きく、人と接するのが好きな方に向いているでしょう。
調剤薬局
調剤薬局は医療用の医薬品をメインに扱っています。しかし、一般医薬品を扱っている調剤薬局では登録販売者が働いている場合もあります。
処方箋の受付や入力、会計、レセプト業務などの事務が多く、パソコン作業がメインとなる場合がほとんどです。
スーパー・コンビニ
近年では、一般医薬品を販売しているスーパーやコンビニなども増加しています。これらの場所でも、登録販売者が勤務する可能性はあるでしょう。
しかしその場合、一般医薬品の相談や販売がメイン業務ではなく、スーパーやコンビニエンスストアの通常業務を行いながら医薬品の相談も受ける形になると考えられます。
登録販売者試験はシニアでも受けられる?
登録販売者試験は年齢や学歴による制限がありません。以前は受験資格として、薬局などでの実務経験が必要といった条件がありました。しかし平成27年に登録販売者制度の改正があり、受験資格の見直しが行われました。
それ以降、年齢等に関係なく登録販売者の試験が受けられるようになったのです。
合格すれば、誰でも登録販売者の資格取得が可能です。試験は各都道府県が1年に1回、例年8〜12月頃に実施しています。
試験内容
試験は医薬品や薬事に関する5項目から出題され、問題数は120問です。すべてマークシート方式で、医薬品に共通する特性と基本的な知識や、人体の働きと医薬品の関連を問うもの、薬事関連法規や制度など幅広く出題されます。
合格率と難易度
合格率は40〜50%程度で、2023年度の全国の合格率は43.7%です。年度や都道府県により、合格率は多少異なります。
難易度は中程度とされており、合格ラインは以下の2つをクリアすることです。
- 正答率が全体の問題数の7割以上
- 正答率が5項目すべてで3.5〜4割以上
しっかりと試験対策をすれば、十分に合格を目指せるでしょう。
登録販売者資格は独学でも合格を目指せる
登録販売者試験に合格するために必要な時間は、約400時間といわれています。つまり、週に12時間程度の勉強をすれば、8〜9ヶ月で知識の習得は可能と考えられます。
もし働いていたとしても、土日を勉強時間に当てれば独学でも合格ラインに達せるでしょう。
登録販売者になるまでの道のり
登録販売者として働きたいと考えたとしても、すぐに働けるわけではありません。登録販売者として働くために必要なステップを紹介します。
登録販売者資格試験に合格する
まずは登録販売者資格試験への合格が必要です。試験は各都道府県ごとに行っており、申し込みは3ヶ月前から開始されます。試験を受けたい場合は、申し込みが遅れないように注意しましょう。
勤務先がある都道府県に販売従事登録をする
試験に合格したら、勤務先がある都道府県に「販売従事登録」を行います。自分の住所のある都道府県ではない点に注意が必要です。勤務先が未定の段階では、販売従事登録はできません。
登録販売者の資格を取得してから勤務先を探す場合は、採用が決定してから販売従事登録を行うとよいでしょう。申請時には、登録販売者試験の合格通知書や住民票のコピーなどが必要です。
実務従事証明書の申請
登録販売者として独立するためには、実務従事証明書の申請をする必要があります。実務従事証明書とは、医薬品の販売経験を証明するための書類で、過去5年の間に2年以上の実務経験が求められるものです。
実務経験の条件は「同一店舗で月80時間以上の勤務を24ヶ月以上」となっています。もしこの条件に満たない場合でも「過去5年以内に医薬品の販売経験が通算2年以上、かつ、合計1,920時間以上ある」場合は、実務経験として認められます。
実務従事証明書は、都道府県のホームページからダウンロード可能です。実務従事証明書を勤務先の都道府県に申請すれば、登録販売者として独立できます。
初めて登録販売者として働く際のポイント
これから登録販売者の資格を取得して働きたい場合、どのような点に気をつけたらよいのでしょうか。知っておきたいポイントを紹介します。
未経験OKの求人を探す
これから登録販売者として働くなら、年齢・経験不問の求人を探してみましょう。登録販売者試験は年齢制限がありませんが、実際の求人は実務経験を条件としている場合もあるためです。実務経験がないうちは、未経験者でも採用してくれる求人を狙うとよいでしょう。
実務経験なしの場合は研修中として扱われる
登録販売者資格を持っていても、実務経験がない場合は、研修中の登録販売者として扱われます。
正規の登録販売者になるには、資格取得後に実務経験を積まなければなりません。研修中の登録販売者は医薬品の販売は制限されますが、レジ打ちや品出しといった一般的な業務は可能です。
正規の登録販売者になれば1人で医薬品を販売できる
研修中は1人で売り場を担当できません。正規の登録販売者になるためには、以下のいずれかを満たす必要があります。
- 直近5年以内に2年間以上、かつ通算1,920時間以上の実務経験
- 直近5年以内に1年以上、かつ通算1,920時間以上の実務経験、加えて継続研修の受講・指定された追加的研修の修了
実務経験は、登録販売者の管理または指導の下での従事が必要です。
また、医薬品を販売するには「1年間で計12時間以上の外部研修を受けなければならない」とされています。研修は毎年受ける必要があり、受けないと医薬品の販売ができません。
押さえておきたい「管理者要件」
1人で医薬品販売が行える登録販売者として働くには、「管理者要件」を満たす必要があります。管理者要件を満たせば、ドラッグストアなど一般用医薬品を扱う店舗の責任者である「店舗管理者」になれます。登録販売者の管理者要件は以下のとおりです。
- 過去5年間のうち、通算して2年以上(合計1,920時間以上)の実務経験
- 去5年間のうち、通算して1年以上(合計1,920時間以上)の実務経験があり、かつ継続的研修並びに追加的研修を修了している
- 通算して1年以上(合計1,920時間以上)の実務経験があり、かつ過去に店舗管理者等として業務に従事した経験がある
- 通算5年以上の実務経験があり、かつ法律に定められた研修を通算5年以上受講している
店舗管理者になれば、キャリアアップや年収アップにもつながるでしょう。
登録販売者の収入はどれくらい?
登録販売者として正社員で働く場合は月収20〜32万円程度が相場のようです。また、パートやアルバイトの場合は時給1,200円〜1,300円程度とされています。ただ、地域や企業ごとに条件は異なります。
長く働きたい場合は、前述した店舗管理者や店長などを目指せば収入アップも期待できるでしょう。
登録販売者とあわせて取りたい資格
登録販売者として働くうえで、あわせて取得すると役に立つ資格も存在します。ここでは3つの資格を紹介します。
管理医療機器管理者
管理医療機器管理者の資格があると、許可を得たり届出を出したりすれば店舗で医療機器の販売が可能です。特定管理医療機器を取り扱いできれば、血圧が気になる方へ電子血圧計を提案したり、肩こりで悩む方に家庭用電気治療器を勧めたりできます。
管理医療機器の管理者資格は、それぞれの分類で指定された講習を受講すれば取得できます。また、講習の受講には一定の実務経験が必要です。
調剤薬局事務
調剤薬局事務は、患者様の受付・電話対応やレセプトコンピューターへの入力作業、調剤報酬の請求などを行う仕事です。クリニックや病院などで働く「医療事務」よりも就職がしやすいメリットがあります。
調剤薬局事務は必ずしも資格が必要なわけではありません。しかし、登録販売者は調剤薬局で採用される場合もあるため、仕事内容を把握しておくとできる業務の幅が広がるでしょう。
漢方アドバイザー
登録販売者はお客様から薬の相談を受ける場面も多々あるでしょう。その場合は、漢方アドバイザーの資格を持っていれば、数ある漢方のなかからお客様の症状に合ったものを選びやすくなります。専用のテキストで一定期間学べば、試験対策は十分に可能です。
まとめ
年齢制限がない登録販売者は、何歳になっても働ける魅力的な仕事です。試験も独学で十分に合格を狙えるでしょう。働く際は、店舗管理者を目指せば給与アップも期待でき、定年後の仕事として狙い目だといえます。
シニア専門求人では、シニア歓迎の登録販売者の求人を探せます。勤務地や業務形態で絞り込んで検索できるため、自分に合った求人を探しやすいのがメリットです。シニア世代になってもいきいきと働ける場所があれば、前向きに楽しく毎日を過ごせるでしょう。
【Q&A】
Q1.登録販売者に年齢制限はある?
A1:登録販売者として働くことに年齢制限はありません。シニア世代でも資格を持っていれば働けるため、登録販売者は定年後でも目指しやすいといえるでしょう。登録販売者資格の試験にも特に年齢制限はないため、何歳でもチャレンジできます。
Q2.登録販売者の試験は難しい?
A2:試験の難易度は中程度とされています。全体の問題数の7割以上正解する・5項目すべてで3.5〜4割以上正解するといったラインを超えれば、合格は可能です。週末などの時間を活用してきちんと試験対策をすれば、十分に合格を目指せるでしょう。